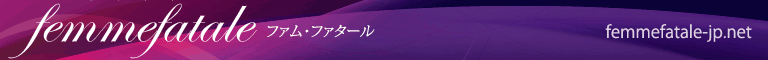モノローグ
タンゴ・革命
このときが来ることはわかっていた。
革命になにもかも捧げているリーダー……彼は私を愛してくれた。けれど、彼の身を案じて不安でたまらない私のそばに帰ってきてくれることはあっても、革命の話ばかり………そしてまた朝が来ると仲間のところに帰っていってしまう。
何日か彼の姿を見ないと、私の心はばらばらになってしまう。
彼がどこかの戦闘でけがをしてしまったのではないか、もうこれきり2度と会えないのではないかと思うと………!
リーダーの片腕である「彼」は、彼からの伝言をときどき私に伝えてくれていた。「彼」とは小さいころ一緒に遊んだこともあるから、彼が元気であること、男達の様子などをおどけて話してくれる。私は子供のように笑いころげる。
彼の様子を知るのは「彼」が話してくれることだけだったから、私は「彼」が来てくれるのをいつも心待ちにしていた。いつも「彼」は私の気持ちをなごませてくれる。「彼」だけが。
ある日「彼」と話しているときに突然気がついた。
私が愛しているのはほんとうのリーダーである彼?それとも「彼」の話してくれる彼…?
私はそれに気づき…うろたえ…彼を裏切った自分を責めた…「彼」の前で。
……では私にとって「彼」はなに………?
私のうろたえを見た「彼」の目。今まで知っていた「彼」とは違っていた…。強い目の光が、鋭く私の心の底を照らし出す。
ああ、神よ…。私はもうまともに「彼」の顔を見ることができない。乾いた唇が、やっと小さな声を出す。
「帰って………」
黙ったまま「彼」は部屋を出ていく。
次の日……彼の弟が手紙を………最後の手紙を私に届ける。
泣くことしかできない。
思い出のタンゴが裏通りから聞こえてきても、悲しいのではなく、とても苦しい。息ができない。昨日までは、彼が私の元に無事で帰ってくれることだけを望んでいたのに………今はもう………。
私は部屋を出て街をただ歩く。いつまでも歩く。
………彼女のことが頭から離れない。
優美な腕、夕暮れの部屋のなかに浮かび上がっていた白いうなじが私の思考を妨げる…。
酒場からタンゴが流れている。
彼女の好きな曲。うれしそうに『初めて彼と踊った曲よ』といった………。
私は扉を肩で押して店に入る。仲間が陽気に声をかけてくるが私はとりあわない。
強い酒を飲んでも、ますます彼女が私の中でふくれ上がる。
さっきの彼女の目………次に会うときが私は怖い。私の心はもう私のものではなくなったのかもしれない。
………明日はきっと戦闘になる。私は彼の隣で闘うだろう。
彼は私の目の前で撃たれた。
そばにいながら、どうすることもできなかった………遺体すら連れて帰ることもできなかった。
彼女になんと話せばいいのか?
だが私は心のどこかで期待している。
私は自分を責める…昨日の彼女のように。そして彼女の家に急ぐ。
部屋に入って行くと、明りもつけないで、目を見開いたまま彼女は泣いている。
「知っていたのか?」と私は聞く。
「彼の弟が………手紙を……。…彼はもう帰らないんでしょう………?」
とぎれとぎれに話す彼女。
「……ああ、マリアさま………」
私は黙ってうなづくほかない。
すぐ目の前にある彼女の顔。涙が次々にあふれだすのを、たった一人で泣いているのを見て私の心はしめつけられる………もう何も考えられない………。
………私は彼女に囚われてしまった。
私が闘いで死んだら、彼女はどうするのか?
彼女のやすらかな寝顔がいとしく、同時に憎しみも抑えられない。
細い首に手をかける。彼女は目を覚まし……私の気持ちなど知らずほほえむ………。私の心に光があふれる。
内戦が始まった。
しょっちゅうアジトを変えなければならず、なかなか彼女の部屋を訪れることができない。
彼女は私を待っている。
私が部屋を訪れたときの彼女の喜びに輝く黒い瞳は、私に言いようのないよろこびをもたらす…しかし同時に大きな闇が私の中に生まれる。
彼女は彼のことを何も話さない。もう忘れてしまったのか………?だとすると、私も死ねば同じことが彼女に起こるにちがいない。
彼女の無邪気なしぐさや笑顔がすべていとおしい。そして、憎い。
彼女に会えない日がつづく。私は連絡係に手紙を持たせる。
彼女からの返事が戦いの日々をうるおす………。
手紙がとぎれとぎれになる。
………彼女になにか起こったのか………?
いてもたってもいられずに、私は彼女を訪ねる………。
「彼」を忘れたのではない。
でも、「彼」は遠くにいて、私のそばにいてくれない…。早く帰って来て欲しいとは思うけれど。
今、目の前にいる彼が、私に太陽のように暖かくすべてを包み込むようなほほ笑みをくれる。彼が話しているときには、悲しみも苦しみも全部忘れて、いつも笑っている自分に気がつく。
このときがいつまでも続くといいのに…。
当局が新しいセクターに期待をかけるのはわかるが、要求されるものはどれをとっても厳しい。新参の俺などに、とてもこなしきれるものではない…引き受けてしまった自分が、恨めしくなる時がある。
彼女が側にいてくれるだけで、俺の疲れた心は安らぐ。 俺に心をあずけて、いつもどんなときも笑っていてくれる。彼女もつらい道を歩んできたと聞いているのだが、そんなことは少しも感じさせないで、俺の他愛もない話に耳を傾けてくれる。
彼女には、前のセクターからの亭主がいることも知った。もっと昔のことも、口さがない連中から、酔った勢いで教えられた。
「その亭主が言ってたんだがな。彼女は女神だと。だけど、猫なんだってよ。おいらにゃ学がねえから、ちっともわからんがね。あんた、わかるかい?」
俺にもわからない。
ただわかるのは、今まで俺のそばにいたどんな女とも違っているということだけだ。
無理ばかり言ってくる上層部や、勝手な下部組織の突き上げばかりの毎日。
仲間は少しばかりの酒を飲んで騒ぐ。それぞれが女の手を取って陽気に踊りだす。
毎日が祭りのようで、いつ戦闘で命を失うかわからない俺たちにとってはこの上ないひとときだ。
俺は、そんなばか騒ぎを座って見ていることが多い。座って笑っている俺を見て、皆が声をかけていく。それでいい。
「……の?」
「なんだって?」
…ちょうど彼女のことを考えていたときだったので、俺は驚いて顔をあげた。
彼女は小さくほほえんで、(いつもの少し鼻にかかった声で)俺に話しかける。
「あなたは皆と踊らないの?」
「ああ。君もそうなんだね」
「ええ。私は…」
「…亭主を待っているから?」
少しの酒に酔い、うっとりと彼女の姿を眺めているのだから、俺は何も考えていなかった。
「……。」
瞬時に、彼女の小さな顔からほほえみが消えてしまう…。
俺は、大事なものを壊してしまったような気になって、彼女にそっと手を触れることもためらったまま、ただ見上げる。
彼女も、ほほ笑みを失ったまま俺を見続けていた。
…時が止まった。
俺の中のどこか深いところに、ひとつの灯がともる。
明かりのない教会の中の蝋燭の火のように小さくゆれて輝きながら俺を呼んでいる…。
彼女の手を取って「踊ろう」と言っている自分に驚く。俺はどうしたんだ?彼女はうなずきも断りもしないまま、俺に導かれるままについてきて、そして俺の腕の中で揺れている。
2人とも、何も話さない。
周りの仲間達が俺たちを見て何か言っているのがおぼろげにわかるのだが、何も聞こえない。俺と彼女だけが、水の底に沈んでいるように何もかもがゆっくりと過ぎてゆく。そうか、これは夢なのか?
その灯は、いつも目の前にあり、俺の中で大きくなっていく。火が近づいてくるのか、俺が近づいているのかわからない。
火は、俺の中に住みついてしまった。
何が起ころうとも、この先ずっと消えることはないだろう。
…夢ならば、構いはしない。
彼女の形のいい額。なめらかな頬に手の甲で触れた。
小さな顔を両手で包む。俺の手の中で彼女は首をかわいらしくかしげ、黒い瞳はきらきらと明るく輝いて、俺に話しかける…。
俺は、彼女の瞳の中の話が知りたくてたまらなくなる。
声を出そうとして、彼女の唇がちいさく動く。まだ言ってはダメだ、そう言うつもりだったのに、俺は彼女のほそく引き締まったからだを強く引きよせたと思うと、何も考えられないままに唇を奪っていた。
甘く熱く俺の中の灯は燃え上がる。まだだ、君の瞳の物語を聞かなくてはいけない…そう叫ぶ俺自身の声が遠く近く、赤い炎につつまれているのを感じる。
なんだ?どこか遠くから、教会の鐘の音が聞こえてくる…。
「…?」
窓から差し込む月の光が、蒼くまぶしい。
光を遮ろうとして顔の前に手を上げたとき、俺は気がつく。
…彼女はいない。
「やはり、夢か。」
両方の手のひらに落ちる窓枠の影が、十字架を形作っているのをぼんやりと見ながら、起き上がって、俺は思いだそうとする。
覚えている…!彼女の輝く瞳、珊瑚のような唇を。
ああ、彼女は女神だ。
…そう言っていたのは、誰だっただろう?
昨日までと同じように彼女と一緒に笑いあっていても、もう俺は元の俺ではなくなってしまった。
彼女の無邪気な笑顔がなによりも愛しい。
彼女は太陽、俺はちっぽけな惑星のひとつみたいにぐるぐる回っている。
あの灯はいつも俺を照らし、背中には長い影を落としている…振り返るといつも、こんなにも弱くなった俺を指さしてひくく嗤う、俺の中から生まれた、俺自身の黒い影。
突然襲ってきた甘くにがい痛みに、拳をつよく握りしめる。…もう一度、いや、夜毎の夢のように何度でも彼女を抱きしめることができたら…。
ある朝、彼女が晴れやかな笑顔で云った。
「彼が、帰ってくるの。あなたにも早く会わせたい。きっといい友達になれるわ!」
俺の中に渦巻いた闇に、彼女が気づくことはない…。
私はアジトに戻った。
夕食前のひととき、女たちは準備に忙しい…煮込み料理のいい匂いがたちこめている。
彼女の姿を目で探すけれども、見当たらない。まわりの女たちにはおざなりにほほ笑みかけ、はやる気持ちを押さえて、夕食棟へ急ぐ。 扉の前に立ったが、すぐに入って行くことができない。久しぶりに会う仲間たちと短い挨拶を交わしながら、私は上の空だ。
…私は恐れていたのか…?私の女神、猫のような真実と不実を…。
いくつもの卓、男たち、女たちの向こうに彼女はいた。
淡い電燈の光が彼女をやわらかく照らしている…そのほっそりした優美な姿にどれほど焦がれていたのか、いま初めて気づく。
彼女が明るく話すようす。彼女の笑顔。ああ、元気でいるようだ…私は安心し、そして私がそばにいなかったことで、少しでも寂しいと思っているところがないかを一瞬のうちに探そうとする。
おや…彼女と話している男…?
そうか、では彼が「その男」なのだな…。
彼と私の両方がここにいることはできない。
…どちらかが去るか、死ぬだけだ…
彼女が選ぶのではない。彼と私の問題だ。
男が、「やあ」と声をかけてくる。
彼が、殴りかかりたい衝動を抑えるのに苦労しているのが私にはわかる。
「よろしく。」
私が差し出した手を、強く握り返してくる冷たい手。彼の男らしい引き締まった顔のむこう側は傷つき疲れ果て、手負いの獣のように血を流している。
彼の思いが私にはよくわかる。
だが、彼女の魅惑的な真実と不実を、彼はきっと理解できないだろう。そして、彼は私のようにじっと待つことはできない。
彼にそう言うべきだったのかもしれない。
……一瞬の魔法の時間は過ぎてしまった。
嬉しさを全身であらわして飛びついてくる彼女を抱きとめる。彼女の長い腕が私を抱きしめると、かぐわしい香りが私の中で駆けめぐり、会えない間に開いてしまった大きな穴をみるみる埋めていくのを感じる。
涙で濡れた彼女の頬。次々にあふれだす涙を唇で受けても受けても止まらない。嬉しさとおかしさで笑いが込み上げてきて震えている私を感じて、彼女もまだ泣きながら笑い始めた。仲間たちにも伝染したらしく、皆で大笑いしながら幾度も乾杯した。
そして、灯を受けてきらきら光る彼女の雄弁な瞳。私だけに見せるその安心しきった笑顔を、幾度戦場の星の下で夢見て追いかけたことだろう。
少し痩せた彼女は、また美しくなった…。
…眠れない。眠れるわけもない。
あの場から逃げ出したのに、頭の中はしたくもない想像が駆け巡り、俺を苦しめる。あの炎が俺の目を、耳を、腕を、手のひらに燃え移り、俺の肉を血を、焼きはじめる…。
彼女のあのほほえみは、俺だけのものだったのに…。それだけは真実だった。
今は、思い出すたびに苦く辛い味が広がってゆく。なのに俺は、俺の中のあの笑顔を、あの炎から守ろうとしている。大馬鹿者だ、俺は!
…もう、これ以上ここにはいられない。
writed by musette/2000
未完のままではございますが… 勝手な妄想です(^_^;)。