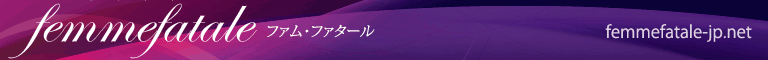モノローグ
パトリシア
カタはついた。だが、こんなのは、おれのガラじゃない。
そうは言っても、しばらくここでやっていく他はなさそうじゃないか?
ディディエとパトリシアには、しばらく休んだらここに帰って来てもらうさ。
奴はあんなことを言ったが、おれにとってパトリシアはたったひとりの大事な肉親だからな。なによりも彼女の気持ちを大切にしたい。
そう…おれが、曲がりなりにもまともに育ったのは、おっとりした親父、そしてなによりパトリシアの優しさのおかげだ。
おれが3歳のとき、実母は死んだ。車の事故だったそうだ。
親父はすぐにおれを引き取ってくれた。けど、パトリシアの母親がそれを気に入るはずもない。なぜかって?パトリシアとおれの生まれた日は3ヶ月も違わないんだから、今思えば無理のない話だ。
新しいママンに歓迎されていないことくらい、小さかったおれにもすぐわかった。
「ウイ、マダム・シュバリエ。ノン、マダム・シュバリエ。」
これが、新しい生活の中で最初に覚えさせられた言葉で、おれの1番古い記憶。小さなおれは目の前に冷たい表情で立ちはだかるパトリシアの母親を見上げている…機嫌をそこねないように、お行儀よく。ふん、嫌なもんだ。
親父は、マダム・シュバリエがいない時には、とても優しかった。だが、マダムが近くにいれば、そんな優しさもどこかへ行ってしまう。おれは戸惑い、いつか諦めた。
マダムがいてもいなくても、変わらずに接してくれたのは家政婦のファジャと、パトリシアだけだった。
おれが正当に扱われていないこと、それについて同情されるのをよしとしないことを、パトリシアはわかってくれていた。いや、何も考えなくても、彼女の中で当然のことだったんだろう。
弱きものを優しくつつみこんでくれる暖かい海。
おれはこんなことを彼女に言ったことも態度で示したこともない。あの家の中で、長くかかえ続けてきた孤独の微熱が、おれを用心深く、硬く、内側に向かわせたからだ。
そして、外への扉はパトリシアに向かって小さく開いている。
彼女はそんなことなんか知らない。
こういっては何だが…それがありがたい。全部筒抜けじゃあ、おれも立つ瀬がないからな。ただ、知らないけどどういうわけだか解ってる、1番弱くて柔らかい場所をつつみ癒してくれる、それがパトリシアなんだ。
けど、ずっと甘えてるわけにもいかないさ。
おれが大学に行くので家を出るとき、彼女は寂しそうだった。おれだって顔には出さなかったが、身を切られるように辛かった…。あれからずいぶん経つ。お互いにもう独り立ちをした。ディディエの奴と結婚して、もう何年になる?7年くらいか?…おれのほうはあい変わらず独り身で気ままな暮らしだが、なんとかやっていける。
ディディエ…あいつはおれと大学の同期だった。優等生だったし、仕事もできて男ぶりも良かったあいつはマダム・シュバリエの大の気に入りだった。けど、本当はパトリシアに好かれたくて必死になってたことをおれだけが知ってる。親父がおれに事業をさせたがっているのを知って焦っていたし、パトリシアとおれとの、説明のつかない結びつきに激しく嫉妬していたっけな。
だから、今度のことはずいぶんとこたえただろうさ。けど、あいつが築いてきたものを全部失っても、パトリシアがそばにいる。
あいつは本当に幸運な男だよ。それに早く気づいてくれることを心から願っている。
おれは、義務を果たせるようここでしばらくやってみるよ。
そして…そうだな、あの王女さまのように、おれの窓も少しずつ広い世界へ開いてみようと思っている。
writed by musette/2003.11.10