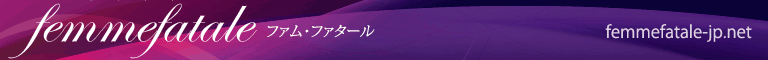モノローグ
エドモン
今夜のサロンも、いつもと同じだな…。
カネを目当てに近寄ってくる貴族のぐうたら息子ども!
どいつもこいつも無能で貪欲な奴ばかり。ヒゲも生えそろっていないような若造でも、カネの匂いには敏感だ。
1代で銀行をここまで築いてきた私には、怠惰だけを受け継いで生まれてきたような貴族たちに、ほとほとうんざりする毎日だった。
だが、あの日のサロンで見かけた彼は、違っていた。
若者だけがもつ、傲慢で刺々しい物腰。艶やかな黒髪に、黒くきらめく双眸。小柄だが、しなやかな身のこなし。そして、なにより彼を際立たせていたのは、たえず周りを圧倒する空気だった。皆が彼と近づきになりたいと願ったが、見えない境界線でもあるかのように、誰も彼のほほ笑みを引きだすことができないでいたのだった。
それは、搾取にしか興味がなく、カネなどたやすく手に入ると思い込んでいるような他の阿呆どもとは何もかもかけはなれた…そう、まだおのれのものは何も持たぬ若造だというのに、とても危険で、魅力的だった。
彼の姿を目で追いながら壁にもたれてそんなことを考えていると、サロンの女主人と話している彼とふいに眼が合い…私に向かって杯を上げ、口の端だけで笑顔を送って見せた。
その不敵な笑みに興味が湧いた。どういうつもりなのだ?
「どちらのご子息ですかな?」
執事は、A男爵家の次男だと云った。聞いたこともない家だ…。
私の念願でもある、政界への進出には、名もなき男爵ふぜいの次男坊では使えない。残念なことだが。
革命をくぐり抜け、資本の力で政治に食い込み、やがては政府までも私たち資本家の手に入れるべくのぞみ、奔走し、身を粉にして働くうち、またたく間に時が過ぎていった。
そして、パリに戻ってきて驚いた。
彼は、あの名門、ランブルーズ侯爵家の婿におさまっていたのだ!
「あなたに会うのは10年ぶりだね。これからもよろしく」
如才なく云いながら、彼の双眸は、あの頃よりも深く昏く、底知れない野心を湛えてゆらめいていた…。
「今のわたしなら、あなたと組めるだろう?」
私をとらえて離さなかったふたつの黒い底無しの湖が、そう語りかけていた。
※きっとこの銀行家は、ヴェルネ氏ではありません(^_^;)。
writed by musette/2004.1.28