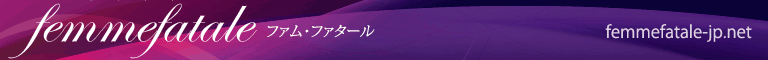パラレルワールド
江戸の黒薔薇(くろそうび)
女の身なりはどうみても町娘ではなかった。
絹地に上品な刺繍を施した小袖に箔をおいた帯は文庫に結んである。もちろん、素足ではないが、おそらく真っ白だったであろう、足袋はすっかり土ぼこりに汚れ、ほころびかけていた。履物すら履けないほど慌てたのか?
どう見ても武家娘。それもかなり高級武家の娘であることは農民出の男にも十分に想像がついた。しかし、その乱れた姿はどうだろうか?
ぶつかって来た時、驚いて腕を乱暴に掴んでしまったが、その瞬間の恐怖に引きつった表情とその直後の安堵の表情。そのまま娘は気を失った。何に驚いて、何に安心したのだろうか?
微かに唇が動いたようだった。
腕の中で崩れ落ちた女に視線を落としながら、男はそんなことを考えていた。
懐の懐剣は豪華な織りの袋に包まれていた。
「お止しよ。そんな、いわくありげな娘に関わり合うのは」
傍らのどうみても男同様、農民出の娘が彼に声を掛けた。
男の名は善吉。声を掛けた娘の名はあみ。……善吉の腕の中の娘の名は判らない。
「こんな格好の娘を放ってはおけねぇし、こんなヤバそうな娘連れじゃあ関所なんて通れねぇ。」
「だからどうだっていうんだい!!」
いずれにせよ、何かがあったのには違いなかった。それならばここで誰かに見られては騒動に巻き込まれることは、どんなに頭の回転が悪くても、容易に想像はついた。
そして、この娘を隠さなければならないことだけは明白だった。
「この間世話になった親方のことにでも転がり込むか……?」
善吉はつい一昨日、空腹を満たそうと忍び込んだ旅芸人一座を思い出した。
諸国を渡り歩き、一座の人間も北の者もいれば南の者もいた。そうだ、あの一座なら、この町娘というにはあまりにも奇異な娘でも十分に隠れることが出来るかもしれない。
新月の闇に紛れて、善吉は娘を背負い河原へ降りて行った。背後に膨れっ面のあみの怒りを感じながら。
さて、時の将軍、春貴公には御台所がなかった。
御台所となるはずだった皇女が、関東へ降嫁されるその日を目前にうら若いお命をはかなくされた為だった。そして現朝廷には、その皇女の他に将軍と釣り合う年ごろの皇女はなかった。
一旦皇女を御台所にと欲した幕府も、また、要求された朝廷もそれ以下の身分の姫が御台所となったではそれぞれに面子に関わることでもあった。そしてそのまま、幕府は御台所を置かず年月は静かに流れていった。
ここに名をお醍の方と申される春貴公のご寵愛を一身に受ける女性がおられる。
もちろん、ご出身家の名からそう呼ばれていた。降嫁できなくなった皇女の身代わりに朝廷が差し出した…と噂されるお醍の方はさる公家の姫君であった。
涼しげな面差しだが、時折り見せるその風情とは相容れぬような強い光りを帯びたまなざしが印象的なお方である。その風評は今だ都におわす頃より都のみならず、遠くこの江戸まで聞こえていたものであった。
細面の白い輪郭を縁どる結い上げられた漆黒の髪。
白綸子の打掛は陽を受けて、その表情をさまざまに変えていた。
大奥の中庭はほのかに梅の香りに包まれている。
庭歩きの共に連れられて、お醍の方は春の気配をかすかに感じる空気を身体いっぱいに吸い込んだ。
鯉でも跳ねたのだろうか、池には静かに波紋が広がっている。
「今し方安里が知らせ参っての」
ふいに声を掛けられ、お醍の方は春貴公のお背を凝視した。
「安里が……何を?」
「駒山藩というのを存じておられるか?」
「いいえ……ご政道のことには疎うございますので……」
静かにかぶりを振ってそう答えた。
「そうよの……おお、由松はいかがか?」
御台所はなくとも、春貴公には何人かの側室があり、すでに4人の姫君と継嗣の君と決まったご長男もおありだった。幕府の先例に習って、継嗣の君を竹千代君と申される。
「相変わらずのやんちゃ振りで、たきを手こずらせておられます」
我が子の様子をお醍の方は嬉し気に語った。
学問をよくされる長子・竹千代君と次男にありがちな濶達な由松君。春貴公自慢のご兄弟だった。
「大事にの。さて、そろそろ戻らねば、いい加減安里もしびれを切らせていよう。しばらくは後処理で忙しくなるやも知れん」
春貴公の後ろ姿を見送るお醍の方の瞳がきらりと光ったように思われた。
どちらかと言えば、政治向きではない春貴公を支えている……と言われるのが
先刻話題の「安里」、神保安里という側用人であった。
出自は平戸藩というこの男には様々な噂が絶えなかった。
神保安里−切れ者と評判のこの側用人は元は平戸藩の下級武士の倅であった。
その母は阿蘭陀人との混血の市井の娘と噂され、そう言われてみれば安里の瞳の色は明るい褐色を呈していた。
他人より頭ひとつ出た、がっしりとした体躯の誰もが振りかえらずにはいられない「美丈夫」。それが安里だった。
その下級武士の倅がどんないきさつで登城が許されるようになり、側用人とまでなったかは、寡黙な男だけに誰も定かなことは解らなかった。だから尚更人々は様々に憶測した。
ただ、今だ年端もゆかぬ十ばかりの頃に年頃の同じ平戸藩若君のお遊び相手として江戸詰めを任ぜられ、江戸に上ったというのは事実のようである。
現在では文武に優れ、上様のご信任厚いこの男は他人のやっかみも手伝って、上様にお目通り許される老中・大名方には、「今柳沢」と噂され、恐れられていることも確かである。
「駒山藩のこの度の所業、きつくご処分あらねば、今後の幕府の行く末に必ずや禍根を残すと思われまするが、上様には如何なるご所存であられましょうか?」
安里は無機質な物言いで、春貴公にそう切り出した。
駒山藩−日本海沖に浮かぶ小藩である。金山を有することで小さいながらも豊かな藩であった。その駒山藩が鎖国を敷くこの日の本にあって、朝鮮との密貿易が露見。事の仔細が発覚することを恐れた江戸家老を始めとする家臣一同が幕府からの使者に対し抵抗・刃傷に及んだ。その上、証拠隠滅の為、騒動の裏で重臣によると思われる付け火まで起こり、危うく駒山藩藩邸の在る四谷近辺では大火となるところであった。しかもそれを指示したのは藩主であったというのがこの一件の最大の問題であった。
駒山藩は金山を守る為もあるかと思われるが、家中の者一同武道をよくし、この斬り合いの際も幕府方、火事のせいもあるが、藩主・重臣を無傷で捕らえることかなわず、藩主をその嗣子共々遺憾ながら死に到らしめることになった。
そして火事の後処理後も、この秋、出雲藩へと婚儀の内定していた大姫の遺体はついに発見されず、行く方知れず…となっていた。
「……きつい処分も何も、藩主も継嗣もなくば、断絶しかあるまい……。あの家は何故か代々子が二人しかおらぬでな…………嫡男・和逸は藩主としてなかなかに期待できる青年であったものを……惜しいの」
春貴公にはいかにも面倒なことだと言いたげに、そうつぶやいた。断絶・お取り潰しとなれば、領地替えがつき物。無骨な駒山藩士のことである。速やかに城明渡しに応じるかどうかも案じられる。また、その役を誰に申し付けるか、金山という大きな付録のついたこの豊かな島にどの大名を配置替えするか等など、気楽に事は進まない。
「大名の配置替えなど、如何にもご面倒であり時間も費用も掛かりましょう。いっそ天領となされまして、上様御自らご管理遊ばされるのがよろしいかと思われますが」
安里は事務的にそう言上仕った。
客のいない芝居小屋のなんと殺風景であり、なにやら、恐ろしげな静寂に満ちたものだろうか。一昨日忍び込んだのは日中の楽屋だったので、ざわざわと落ち着きのない小屋の雰囲気であったし。
あれほどいた男衆の姿も今宵はまるで今までまったくいなかったかのように気配がない。
奥から人の気配に気づいたのだろうか?親方の姪っ子というこの一座の花形の踊り子・あきのが飛び出してきた。
「誰だい!!……この間のこそ泥じゃないのさ。どうしたんだい?……その荷物は……」
善吉が背中から降ろした女の姿にあきのは目を丸くした。
「峰之丞の親方はいねぇのか?」
「男衆はお楽しみの最中だろうさ。それで?何の用だい?」
「この女……親方なら匿えねぇかと思って」
「お武家さんのお姫さんじゃないのさ……あんた……何したんだい?」
「何もしてねぇよ!!」
善吉は事の次第をあきのに話した。もっとも、善吉だとて、どうしてこんなことに関わっているのか分かってはいないのだが。
楽屋の一角に薄い布団を敷き、その上に帯を解き、襦袢姿にしたこの名も知らぬ姫を横たわらせた。姫はぐったりと力なく眠ったままだった。
あきのがしげしげと姫の着物や懐剣などに見入っている。ふと懐剣に小さな家紋が彫っているのに、気づいた。
「……すずめ……どこだかで見たことあるような……?」
雀紋というのはそう多い家紋ではない。家紋など無縁の貧乏百姓の出の善吉は物珍しそうにあきのの手元を覗き込んだ。
「駒山藩の袱紗だろう」
「順之助!!」
その声に善吉は後ろを振り返った。
背後に気配も感づかせず立っていたのはこの一座の裏方を引き受ける大男だった。一座の男衆は華奢な者が多い。その中でこの男は印象が強かった。善吉も背の高さだけは村でも、この江戸でも誰にも負けなかったが、順之助と呼ばれたこの男はひょろっとした善吉とは比べ物にならないくらい逞しい体つきだった。
旅回りのこの一座は、去年の夏を暑さから逃れて、日本海沖のかの小藩で興行していたのだった。その際評判を聞こし召したお国下がりの最中だったご城主様の招きで城内の宴に華を添えることになった。その時この一座の出し物に大いに満足された殿様より特別のご褒美として駒山藩のご家紋入りの袱紗に包まれた金十両もの大金を賜ったのだった。
金糸で刺繍されたふくら雀が対を成した愛嬌のあるこの可愛らしい家紋をあきのが気に入って藩主ご下賜のこの袱紗を欲しがった……ということをあきの自身思い出していた。
「ってことは……あの金持ち藩のお姫さん?」
「そうじゃなくても、どう考えても藩の人間だなぁ……」
順之助と呼ばれた男は姫の血の気の引いた寝顔をじっとみつめていた。
夜半過ぎ、小屋の表が何故だかざわついていていた頃、うっすらと姫の瞳は開かれた。しかし開かれた瞳は何かを凝視しているようで、何も見ていないようで、ただ、見開かれたまま一点を動かなかった。傍らの順之助が口を開いた。
「名は何と申される?」
「円(まる)と……」
問われるままに、以前そう呼ばれていたであろう名を姫は機械的に答えたが、以後、その口が開かれることはなかった。
無用に日だけは経っていったが、口以上に瞳は何も語らず、円と答えたこの姫が持ち物と着ていた物から「恐らく駒山藩主の一姫」であろうという推測しかできなかった。
そして、日が経ち噂に聞けば、駒山藩江戸藩邸が火事で焼け落ち、藩主はその嫡男−和逸共々命を落としたという。そして藩主も継嗣も失った駒山藩の取り潰しが庶民の間でも噂として流れていた。
そんな噂とここへ連れてこられた状況から何かわけありなこの姫を身なりだけは一座の娘のように仕立て上げ、世間の目から逃れさせた。
そしてあの夜以来、何故か善吉が小屋に入り浸るようになっていた……。
大川を渡る風はほのかに梅の香りを含み、春が間近なことをそっと告げていた。
「ご政道には疎うございまして……とはまた吾がことながらおかしなこと……」
お部屋に戻ったお醍の方様は自分の言葉を反芻しながら一人自嘲するかのように笑みを含んでいた。
安里が来たということは駒山藩取り潰しの件を上様に言上するということ。そして天領となったあの島の利権は幕府のもの。政治の実権は安里が握っている、安里の言うことであれば春貴公はなんであれ、受け入れられる。春貴公の寵は妾がもの……安里との仲は今だ誰の知るところではない……お醍の方はいずれ自分の懐に落ちてくるであろう富を想像しては笑いが止まらなかった。
−安里との仲……。なぜこうなったのか?お醍の方自身もそして、恐らくは安里自身も解らなかった。互いに求めたのは心でも身体でもない、それだけは確かなことのようであった。そう「愛しい」という感情は安里に対して持ってはいなかった。それは安里も同じであろう。何かが呼び合ったのか、それが神仏の御心なのか……。
春貴公との婚儀は傾きかけた公家の姫であったお醍の方にはまさに晴天の霹靂なことだった。春貴公の御台所と決まっていた優子内親王様が急な病を得られてお隠れになった……というのはあまりにも有名な話しであったが、無論それは表向きのことであった。
東下りをどうにも承服されかねた勝気な内親王様が主上様に無断で髪を降ろされたのであった。このたった一人のお妹君のご決心を主上様も無碍にはおできになれず、そのまま意を汲まれて大原の奥で優子内親王様は幕府の目を逃れてひっそりと仏門に帰依されることとなった。
内親王様ご自身のことはそれで片を付けられたが、片付かないのは幕府の方だった。幕府の面子と朝廷の面子と、そして双方の関係を悪化させたくないのは何より朝廷の方だった。
そして御台となるはずだった優子内親王の代りに春貴公の側室として朝廷から召し出されたのが、九条醍醐家の鞠子姫……お醍の方その人だった。
雅を好む実家が時代から取り残され零落の一途を辿るのは、鞠子姫にとって忍びないことであり、自分が側室として東へ下ることで家門が生き残れるのであれば自分の想いなど我慢すればよいことであった。しかし内親王のわがままの為に己の人生を狂わされることだけは我慢のならないことでもあった。この美貌がそんな人生を招いたのであれば、自慢の美貌も疎ましいだけであった。江戸など行きたくて下るのではない。野蛮な武家の頭領など傍に侍ることを想像しただけで我慢ならなかった。それが側室にあがれば夜伽も当然のこととなればこれほどの屈辱があろうか、この怨み、いずれなんらかの形で晴らさんと……鞠子姫にとってその想いだけが長い道中を、見知らぬ江戸での生活を耐えるための糧であった。そして月日は流れていったのであった。
「この怨み」……それが誰に、何に向けられたのであるのかは鞠子姫自身定かなことではなかった。だが、零落する一方の力のない実家の為にこうなったのであれば、誰よりも強くなりたかった。何よりも権力が欲しかった。その為なら風雅とは言えない江戸好みに装うことも、大奥での評判を得ることができるのであればそうしたし、夜伽も苦にはならなかった。なにより、男子を挙げることを自ら進んで望んだ鞠子姫は側室に上がるや、将軍家の信任の厚い高僧にその為の祈祷を命じた。
子供が欲しいのではない、むしろ、野蛮な武家の血など吾が血統に一滴の血も混じらせたくはなかった。だが、女の身で権力を手中にするには男子の母となるしか方策はなかった。今のこの国において権力の全ては将軍家のものであった。ならばいずれこの国の将軍となる将軍家の嫡男の母としての立場が欲しかった。継嗣があろうが、まずは男子を産み参らせ、その母とならねば何の望みも持てないことは公家の世界も武家の世界も同じことだった。……そう、形のないところには何も落ちてはこないが、形のあるものなら、なくせばよいのだから……。
そして、そんな火のような想いのすべては涼しげな面差しの下にすっかりと隠すことが何よりも重要であることも、お醍の方は知っていた。
呼び合ったのは同じ心だった……。
安里をここまでのし上がらせた想いの根底にあるものは「怨み」であった。安里にとって、自分以外の他者はすべてが敵だった。生まれた時からいや、ひょっとすれば生まれる前から全てに疎まれていた。
遊女の母を持つ女は結局は遊女になるしかなかった。
血の半分に阿蘭陀人の血の混じる母は真っ白な父譲りの肌の色と日本人の持つ肌の滑らかさを併せていた。髪も瞳も茶褐色。それだけで十分見世物としての価値はあったが、母は天女もかくあるやと思われるばかりの美貌の女性だった。そんな遊女を父の如き下っ端役人がどうやって見受けしたのか、息子の預かり知らぬことであったが、たしかに母は父の子を身ごもり、産み落とした。例え男子を挙げても遊女であった女が武家社会で受け入れられるはずもなく、母は決して幸せな生活を送ったわけではなかったという。そして生まれた子も純潔の日本人というにはあまりに明るい瞳の色を持っていた。徐々に平衡感覚を失っていった母親は己の姿を、そして己の生んだ幼子を見ては半狂乱になり、その果てに自分の命まで落としてしまった。母親が自らの命を散らしたのは安里、5才の年のことだった。
気違いの母親の子、毛唐の血を持つ子は誰からも疎まれ、嫌われた。そんな孤独な子供にとって道場で、藩校で一番になることだけが自らの価値を認められる場所だった。甘えたい盛りの子供は他人の目から知らず知らずのうちにそのことを学び、その為の努力と行動をした。
天女の美貌の母が彼に残してくれたただひとつの贈り物は誰にも勝る美貌だった。
そして……藩主の目にとまった文武に秀でた美貌のこの下級役人の幼い息子は、江戸に上がるようになった。
自分以外は全て敵と思うことで、全てに「怨み」を背負うことで、わずか10才の男子は「今」から
のし上る為の第一歩を踏みだしたことになる。
ここ最近、江戸市中を騒がす『黒薔薇(そうび)団』と呼ばれる盗賊の一団があった。
狙うのは悪徳商人と陰でささやかれる大店や、悪い噂の絶えない大名・旗本ばかり。いかに大店だろうと、小金を貯め込んだ武家だろうと、悪い噂の無いところからは奪わない。そして、奪った金の一部は貧しい長屋にばらまかれるため、町人達からは義賊と評判が高かった。神出鬼没のこの盗賊団に火盗改めもほとほと手を焼いていた。
その頭目は身の丈七尺あまりもあろうかと思われる美丈夫と噂され、その噂も手伝ってか女達にまで人気があった。
そんな盗賊団が貧しい者達から人気があるのにはもうひとつ、不確かな噂もあった。あるところに頼みに行けば、頼み人の代りに『黒薔薇団』が怨みをはらしてくれるというものであった……。
円がこの一座に匿われるようになって、もう一月ほどが過ぎた。相変らず何もしゃべろうとはしないし、時折、小屋の格子戸から何を眺めるでなくじっと外をみつめている。
そんな円の傍らには何故か善吉の姿をよくみかけた。この頭は悪いが気のいい若者はなにくれとなく円の世話を焼き、あみの不評を買っていた。
乗りかかった舟だからというばかりではない。これまで善吉の周りにいた女達とは明らかに違うこのもの言わぬ姫のことがどうにも放っておけなかったのであった。
何か話しかけてもおどけても、振り向くでもなく、笑うでもないこの姫が……。
それはあきのも同じだった。
誰とも交わろうとしなければ、食欲旺盛な男衆の食事を粗末にしてまでわざわざ分けてやっているせっかくの食事にもほとんど手をつけない。
何もせずにただ、ぼけっとしているだけの役立たずの女なんかをただでいつまでもおまんまを食わせてやってられるほど、こちとらお気楽な生活をしているわけじゃない。それでも、この姫が放っておけなかった。どうしたら何か反応してくれるんだろうか……?
笑えばきっと可愛いんだろうに……。
ふと、あきのは去年、今はもうなくなったかの藩で覚えた子守唄を思い出した。駒山藩の姫なら、国許は知らなくてもひょっとしたら聴いたことくらいあるだろう……。
「朝の光りに きらめく夢は
赤い花咲く 故郷の丘
そよぐ風に鳥は歌い あの日の頃の 母の言葉
今も心に咲き香る 花のふるさと……」
向けられた瞳にみるみる涙が溢れてきた。
「……兄上が歌ってくださったお国の歌……嫁ぐことの決まった私に……国の歌の一つも覚えて参れと……いったいどうしてこんなことに……」
とぎれとぎれに聞かれた円姫の言葉からは幸せに育ったであろう姫の一人では負いがたい深い絶望が伝わってきた。泣くことすらもずっと忘れていた円姫は、あの夜以来はじめて声を挙げて泣いた……。
あの日……
幕府の使者が藩邸を物々しく訪れたのは何時だっただろうか?春まだ浅い弥生の暮にはまだ半時もあっただろうか?兄と二人、出雲藩へ輿入れの為に作らせた、粋を凝らした道具の数々や、着物を見ていた頃だったか……?表の騒々しさが奥にまで伝わってきて、兄は「何かあったら隠し通路から逃れよ!」
と一言だけ残して、そして……表で火の手が上がった……。
火はまたたくまに藩邸を包み込んだ。円姫の部屋の目の前まで火の手が迫って来た頃、円は乳母の手で通路へ押し込められた。
「ちずも直ぐにお後を追いますゆえ、まずは姫様、後ろは振り向かずに藩邸の外まで逃れられますよう!!」
……その言葉を信じたわけではなかった。今ここで逃れなければあの火勢では逃れられるはずはない。それでも「逃れよ」と誰もが自分に叫んでいた。打ち掛けの裾をたくし上げ、必死に走る円の耳に断末魔の女の悲鳴が聞こえた……。
耳をふさぎ、乳母へ何度も「ごめんなさい」と唱えながら、ひたすら走った。
走るうちに打ち掛けはいつのまにかどこかで脱げてしまった。帯が苦しい……。
部屋からそのまま出てしまって、足元は足袋だけの姿である。いつか追っ手が追いつくのではないか?幕府の使者が来たのではなかったのか?なぜ表で火が付き、私は逃げなければならなかったのだろうか?何故?何故??
何も解らないまま、円はいつのまかに暗くなった外に居た。藩邸からほとんど出たことのない、深窓の姫には、己の身に降りかかったこの事件が何であるか知る由もないことだった。
新月の闇夜はそれでも、この姫を優しくその闇に包み込んだ。
writed by ぽりーん