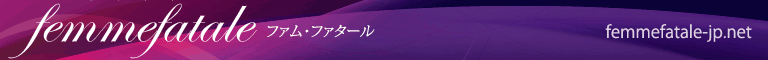パラレルワールド
砂漠の黒薔薇・お江戸編 第1章
「紗味の局様」
「おお、采女か、挨拶などよい。近う寄りゃ」
とある小藩の下屋敷であった。
御台所亡き後、大奥での権勢著しい紗味の局のお宿下がりである。
判を押したように毎度欠かさず尋ねてくる当藩の江戸家老、樫務采女。
「春千代ぎみは御変りございませぬか?」
相好を崩して局「壮健じゃ。采女、そちの方はどうなのじゃ?」
「わたくしの方でございますか?着々と…」何やら企んでおる様子。
「頼もしい限りじゃ…。有洒公が水戸家お預けの間に我が子の地固めをしておきたかったけれど、最早致し方ない。吉宗公は八男で上様におなりになったのじゃ。それを思えば春千代も」
「おっと御局様、お声が大きゅうございますぞ」
「妾としたことが。ほほ。ほほほ。」
気を良くしたか采女は、更に局の傍に寄り、その手を取ってこう云った。
「それよりも御局様。今宵は」
「ほほほ。早う上様も…のう、采女。」
まんざらでもない様子に樫務は更ににじり寄って耳元に囁く。
「薬師に天竺の毒を調合させて居りますれば、ほどなく…」
「やっぱりな。有洒さまの読みは当たってたって訳だ。同じ穴の狢かぁ。ひでえ話だぜ」
天井裏で息を殺していた舎助は声に出さずに呟いた。有洒公の子飼いの草の者である。
「そうか…。ご苦労、舎助。ふん、懲りぬ奴腹だ」
草の者を還した有洒は、縁側に寝そべって独り呟いた。秀でた額をもつ横顔が十六夜の月に照らされている。
将軍の嫡男でありながら、御台所が不審な死をかこった折りにあらぬ疑いを掛けられて水戸家に預かりになって3年。お上も詮議を諦め、ようやく有洒は許されて御膝元に呼び帰されたのだった。
たくましく成長し、周知が認める武勇と美丈夫振りが、御城の腰元から上臈までの噂話に花を咲かせたが、当の本人はそんなものは煩わしいだけ。どこ吹く風の呈で気ままに城内を歩き回るので、父将軍もどう扱って良いものか決めかねていた。
「春千代は、母局とは違って、純な奴だ…。たった独りの弟は悲しませたくはないが」
「兄上。ここにお出ででしたか」
「おお、春千代。ここに来て一杯やらんか?」
もうすぐ元服を迎える弟に徳利ごと渡してやると、目を丸くしながらも一口呑んで返してきた。久しぶりに逢うた兄が慕わしくてならないのだ。有洒にもそれはわかっていて、この兄弟は周りの思惑を気にもせずに酒を酌み交わして語り合うのだった。
「春千代、お前の母上は元気か?」
「母上ですか?はい」
「そうか、元気か。ならば、閉じこめて置くんだな」
「何故ですか?」
素直な応えに有洒は笑いながら「人生は短いからさ、春千代。今この時を大切にするんだ」…そう云って体を横たえ、目を瞑ったと見たらもう寝息をたてて居る。
「…兄上?」
春千代は、先程の無邪気な様子とは違ってどこか寂しげな眼で兄の横顔を見つめて居る。やがて、己の羽織を脱いでそっと掛け、音を立てぬよう気をつけながら引き取って往った。
--------------------------
「…有洒さまはお変りになられた…お前もそう思わない?お優」
「いえ、大納言様は私のような者にまでお優しお声をかけてくださいますよ、茉莉姫さま。きっとお久しぶりに姫さまのお顔をごらんになったので、お美しさに驚かれたのでしょう。」
「そうかしら…。私はお輿入れのためにお国を出て、道々咲き誇る桜の花を愛でながら江戸に向かって…お城についてすぐだった。忌まわしいことが立て続けに起ったのだわ。あれからもう三年。私はあの方をここでずうっと待って待って…」
近ごろの茉莉姫は、最後は我知らず独白になってしまう。
お優はいろいろと気を配って姫の薙刀の相手などしてなにくれと気晴らしを見つけてやる。姫もなにかと「お優、お優」と呼び立てるので、二人は仲の良い姉妹のようであった。
質実を家訓とするお家柄であったので、大身の姫君でありながら供もあまり連れずに国元から将軍家に輿入れしてきたのだが、三年前の有洒の水戸家お預けで身の廻りを世話する者も徐々に国に呼び戻されていったのだ。
今では、茉莉姫が心打ち解けることができるのは、茉莉と共に国から付き従ってきた数人の侍女のみであった。…もともと国元では闊達で鳴らした姫のこと、うるさいお部屋付きなど居らぬほうが益体もない城中の噂話も聞かずとも済めば、がみがみ怒鳴られずに済むので、端の者の懸念など素知らぬ呈で気楽に過ごしていた。
それが、有洒がご赦免されて戻ってくることを知り、茉莉姫も安穏としていられなくなったのであった。
「月が…」
かろく打掛を引き寄せ僅かな衣擦れの音も聞かせず、ついと立ち上がって春の月を見上げる茉莉姫。このところよく見かける憂いを帯びた眼差しをあげて、月明かりの中に立ち尽くし、何を想っているのか。
有洒が、入り組んだ廊下の遠い端にそっと立って、そんな茉莉の姿を飽きず見つめていた…。
----------------------------
この日、将軍家恒例の春の宴が本丸で行われる。
広大なお庭には提灯がにぎやかに飾られ、皐月のさわやかな風が新緑の枝を揺らして、気持ちの良い夕暮れどき。
有洒が帰ってきたということで、大目付から特別に許されて、近ごろ評判の旅芸人一座の芸も見れるとあらば、宴席に連なる公方気に入りの者共、奥の女たちにとってもまことに心浮き立つ思いである。
宴好きの将軍家と紗味局、好奇心おう盛な春千代も目を輝かせて一座の芸を今か今かと待ちわびていたが、宴の主人公であるはずの有洒はなぜか浮かぬ顔で漫然と月を眺め、侍女の酌も断って酒を呑んでいた。
茉莉姫は、己の思いに気を取られていて南蛮芸どころではなかった。案内された席は有洒から遠く、がっかりしたと同時に
「お隣にいても、何を話してよいものやら…」
と、ほっとしてもいたのだ。
共のお優は、そんな茉莉の様子は手に取るようにわかってはいたが、今は目の前に供された好物の水菓子のほうが大事だった。
「さてもさても、ご尊顔を拝し奉り恐悦に存じます。今宵はめでたい春の宴。また、大納言様がつつがなく戻られたお祝いの宴でもあるとか。この把葉、南蛮じこみの芸の数々をご覧に入れたく参上つかまつりましてございます…」
などと座長が長々と挨拶をするのに、この場を取り仕切る側用人筆頭・祐木美濃守が苦笑しながら先をうながす。
「これ、前口上はもう良い。早う舞って見せろ」
ははあ、と平伏して把葉、鈴がついた異国の鳴り物をひと振り、ふた振り。
金銀の飾りをつけた男女が十数人、滑るように現れた。手足につけた鈴を鳴らして軽やかに舞う。みな日の本の民のようでではあるが、髪を赤く染めてきらびやかな布をかぶって紐で締め、色鮮やかな薄物をまとい、体が透けて見えるものもいる。
そのような男女が手を取りあって踊る姿があまりにも珍しく、並み居る者たちは身を乗り出してむさぼるように見物しているのだ。
長身の男が歌いだした。
遠い異国の砂漠を越えて
夢のあらびあ
星の四十万に誰が吹くのか笛の音が
夢のあらびあ魔法の国
夢のあらびあ魔法の国
これもまた、聞いた覚えもない異国の旋律や言葉に、将軍家をはじめ、重臣や女たちもすっかり魅了されてしまった。
まるで下々の者どものように、やんややんやの大喝采である。
その者たちの間で、酒を呑みながらひとり醒めている有洒。
物思いに沈む茉莉姫。
油断なくまわりを見回していたのは、南蛮一座の差配をした褒美に、宴の末席を恐れ多くも頂戴した樫務采女であった。
----------------------------
「上様も大層お喜びだったな。ご褒美はたんといただけよう。な、お三須」葉杷は商人のように手揉みをしながら満悦である。
「そうね、たくさん頂戴しなくっちゃ。新しい着物もたくさんこの日のためにつくったんだからね。」ふくらんだ袖や、天竺から取り寄せたというやわらかい布を足首のところで絞った足通しには、さまざまな鈴を縫い付けてある。小さく足を踏みならして鈴を鳴らしながら、むすめは答えた。
一座の花形踊り子である三須は、三須の母は葉杷にとっては妹だ。三須がまだ幼いころ、母が亡くなってしまったので葉杷がひきとって育て、長じて旅芸人となった。今では一座の細かいことにもいろいろと目を配ってくれるしっかり者である。
「わかっているとも。三須や」
「あ、待ってよ、矢湾!」葉杷が云い終わらぬのに鈴の音を残して、あっという間に先を行く一座の者たちの方へ走り去ってしまった。
「やれやれ。元気なむすめじゃ。」首を振り振り困ったふうであっても、やもめの葉杷にとっては妹の忘れ形見が愛しくてならぬようである。
三須が追っていったのは、先ほど歌っていた長身の若者である。
かれも、髪を赤く染め、艶のある長い布でその髪を覆っていた。群青いろの袖無しの上着のくりには色とりどりの玉石があしらってあり、かれの赤い髪によく映っていたし、白の足通しは、かれの上背をいっそうきわ出させていた。
「矢湾ったら!」
「なんだ、三須か」振り返って云う。
「なんだとは何よ」
「なんだとは何よたぁ、なんて言い草だ。…まあ、いい。俺は考えてるんだ。ほおっておいてくれ」
(いつもの他愛ない言い争いが、また始まった…)そう、周りの者も思っていたのだが、いつもやり返す矢湾の様子が少し、おかしい。
三須も調子が狂ってしまって、遊んでもらえなかった猫のように、どうしていいかわからなくなって急に走り去ってしまった。
(おい、おい…どうしちまったんだい)と見送る一座のもの達。
それにも気がつかず矢湾は、ふところに縫い止めた守り札をきつく握りしめていた。
(父上、兄上、見守っていてください。眞留、おまえもきっと探しだす。そして樫務、宴にあいつの姿を見た。貴様の非道のかずかず、忘れておらぬぞ…)
そのときの矢湾の顔つきを見ても、先ほど歌っていたときの陽気であけすけな男でと同じだとは誰もわからなかったであろう。
顔を上げたときには、若いけれども一念を秘めた、鋭いさむらいの目にかわっていた…。
-----------------------
同じころ。
お堀端に、むすめの姿があった。
そのむすめが、人目を引いたのも無理はない。
漆黒の髪は束ねて巻き付けたうえに飾り紐で結わえ、どことなく異国ふうであったし、着物のほうも、上等なものでないが、はっきりとした色づかいの生地には珍しい縫いとりがしてある。何よりも、むすめの猫のような、くっきりした芯の強そうな双眸がどこともわからぬ異国ふうのいでたちに良く映えていたのだった。
行き交うものたちが、必ずといっていいほど振り返る。
(伴天連かぶれの娘かえ…)と、蔑むものもいれば、(仇っぽくて、いい娘っこじゃねえか)と、うしろ姿にぴゅうと口笛を鳴らすものもいた。
だが、そのむすめ阿弥奈は、どこ吹く風の呈で、上機嫌でぶらぶらと歩いていた。
「よお、阿弥奈」
「善の字じゃないか。なんだい、薮から棒に…」
声をかけてきた男も、これまた阿弥奈と同じように異国の匂いのする出で立ちであったが、どことなく板についておらぬ。
細身の長身であるかれを更に際立たせていたのは、その腰の大小だった。
(おいおい…かぶき者の二本差しかい。物騒だねえ)
よく見れば悪者ではないのはわかるのだが、そこに居合わせたもの達は、どことなく及び腰になって(善の字)と呼ばれた男から遠のいていく。
目利きのものが視れば、平常心ながらもその男の足捌き、目の配りようで、なかなかの遣い手だと踏んだであろう。
「そう云うな」
破顔した男のかおには、健やかな明るさと屈託のなさが見て取れる。
その出で立ちに似合わぬ育ちのよさ気の良さ、面倒見のよさ。
いちど悪党を軽く懲らしめてやってから、長屋の女たちは「善さん、善さん」と夢中であった。
当然、阿弥奈は面白いはずもない。
writed by musette